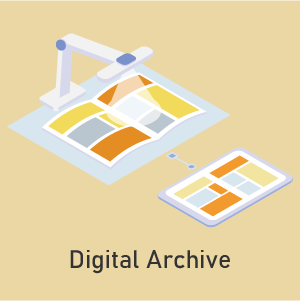デジタルアーカイブ 第1回
デジタルアーカイブの課題
私はほとんどを秋田県立図書館で勤務しました。その際、日本の公立図書館では初めてとされるデジタルアーカイブを構築した経験があります。また2年間ですが、国立国会図書館の電子図書館課に出向し、自身が提案したレファレンス協同データベース、当時あまり注目されていなかった電子情報の中長期保存研究に携わりました。
現在は、内閣府知財戦略本部のデジタルアーカイブ関連の有識者会議と総務省の地域情報化アドバイザーを通じて、全国の公共施設のデジタルアーカイブ構築のアドバイスをしています。
近年、多くの機関や企業がデジタルアーカイブを積極的に構築、公開するようになりました。一方で、デジタルアーカイブには様々な課題が表面化してきました。前述のとおり全国の自治体を訪問し始めてから15年程になりますが、その間、相談された内容の一部を紹介してみましょう。
「保存データを作成していないため、もう一度原本から作り直すこととなった。」
「デジタルデータの品質が低く、現在の要求レベルに合わない」
「コンテンツの追加がされていないため、アクセスが少なくなった。」
「維持費用が組織にとって大きな負担となっている」
「特殊なシステムでデータの移行ができない状態である」
このように既に原本を裁断した、廃棄した等、タイムマシンでもない限り解決できないケースもあり、知識不足がデジタルアーカイブの消滅や停止に及ぶことがあります。
丁寧に制作されたデジタルアーカイブは各地域における文化や歴史の普及に貢献し、今後は子供たちへの教育面でもその活用が大きく期待されています。しかし、デジタルアーカイブの専門知識を持つ職員が組織内に不足しており、どのようにして、デジタルアーカイブに取り組んでいけば良いのか悩む方も多いと思います。そこで今回はデジタルアーカイブの概要とその構築ポイントについて数回に分けて解説したいと思います。
デジタルアーカイブには、いくつかのフェイズがあります。それはデータ制作、システム構築、活用、保存、人材育成です。これらに加えて著作権の知識も必要になりますが、ここでは、それらについて説明します。