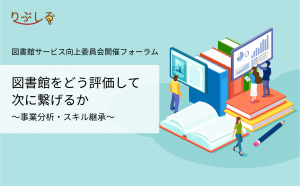岐阜市立中央図書館 -みんなの森 ぎふメディアコスモス-
3.11の衝撃を受けて ー交流ができる図書館をー
なぜ岐阜市立図書館の館長になろうと思われたのでしょうか?

総合プロデューサー 吉成 信夫氏
吉成:私が東京にいたころはコンサル業に従事していて、その時は自分が図書館業に携わるとは思ってもみなかったです。書店の方が身近にあり、日比谷の図書館や都立図書館はよく使っていましたが、敷居が高く”調べものをする場所”というイメージでした。
1996年から岩手に移住し、廃校という元々パブリックであった場所に広場を再構築するという目的の元、「森と風のがっこう」という実験的な環境教育的空間づくりを地域の人々や学生・子どもたちといっしょに実践していましたが、3.11が起き、かなりの衝撃を受けました。
沿岸部には旧知の友が多く住んでいる。すぐに現地に向かい何か出来ないかと、少しでも助けになればと、太陽光パネルや温水器を設置するプロジェクトにも参加しました。
その時、全国各地から私のNPO宛てに本が送られてくるようになりました。それも校舎に入りきらないくらいです。
当時、”復旧”ではなく”復興”という言葉が掲げられていましたが、“公民館”らしい場所をもう一度、世代を問わず人と人が会話・交流できて息抜きできる場所をと考えたときに公共空間としての”図書館”が必要なのでは、と思いました。
なぜ図書館がふさわしいと思ったのでしょうか?
吉成:私は、公共の県立児童館に7年従事していましたが、やはり児童館では預けられる子どもとその親の世界で社会との接点がまだ弱いと思っていました。
図書館をマネジメントした方が、より地域と社会と近くなり、本があることで対話や自由に語り合える場に繋げていけると感じて、公共図書館でやるべきだと思いました。
初めは被災地の図書館で館長をしようと考えましたが、Facebookで岐阜市立図書館の館長の募集が出ていることを知り、これからできる被災地の図書館のモデルのヒントにもなるものを作っていければと思い応募しました。
共に創っていく
吉成:昔、岩手県東山町(現・一関市)で開館させた「石と賢治のミュージアム」ですが、自分が退職した後に観に行くのが怖かったんです。自分が開館に深く関わったものが、もしかしたら酷い状況になっているのではと考えると辛い…。
しかしですね、10年経って別件で一関市に招かれた時に立ち寄ったのですが、ミュージアムは展示も設備も充実して活力が増していたんです。私が企画した看板講座「グスコーブドリの大学校」も、22年を経て今も健在でした。
文化的公共施設は人に依存し停滞することもあれば、さらに成長することもあると深く学びました。
岐阜市立図書館は館長に就任してから開館まで3ヵ月しかなかったので、デッドラインが決まっている中で、私は走りきるしかなかったです。これまでの本を貸すだけの市立図書館ではなく、仕組みをガラリと変えました。
私は司書出身ではないから選書は専門ではない。そのため、展示物をどうするかやあらゆる事業の企画に入って、司書たちと一緒に企画することに。 それを開館当初から9年目の今に至るまで続けています。
こちらの図書館は館自体もそうですが展示も含めレベルが高いなと感じます。
吉成:ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。
色々と手が込んでいて時間がかけられているような気がしました。
吉成:開館する年、正規の職員は、どうしても目の前の事務の仕事などに忙殺されていました。
であれば、非常勤の職員もすべて一緒にやってみながら、みんなで思いを言葉化しながら意識を変えていきました。
中央図書館の職員は70名程います。意識の共有が職員の意識を変えていくことにつながるので今でも、毎日の朝礼は特に大切にしています。
中高生からのどんなお悩みにも司書が答える「心の叫びを聞け! YA交流掲示板」では、対応してくれている5名のメンバーと回答に関する意見交換を今も行っています。
意識の共有は難しいけど、大切なことですよね。
吉成:実はもうすぐ、柳ケ瀬商店街にオープンする高層ビルの中に子育て施設ができるので、そこで本の供給や読み聞かせをしてほしいという要望があります。館内の造作や備品の選択までアドバイスの実施をしています。
連携した出先が初めてできるので、新しい形に膨らませていきたいと思っています。 これまでメディアコスモスを中心に事業を広げてきたところがあるため、これからは他の分館や図書室で同等なサービスが供給できるようにしたいとも思っています。
これからの未来をもシビックプライドに
1階で「シビックプライドプレイス -ぎふ古今-」をご紹介いただきました。市民からデータを集める事業はこれからもっと活躍していきそうですね。
吉成:情報エリアの設置は、本当は図書館でやりたいと思っていました。しかしそれでは図書業務が回らなくなってしまう。
メンバリングを考えながら、外に部署を作り、その部署が図書館と連携するというやり方にしました。
市民の人から集めた写真のデジタルデータは図書館に保管されることにし、そのデータの使い方は担当部署に検討させることを想定しています。
岐阜市は観光地なので、観光政策をより良くするためには、街のことを知らないといけない。 その考え方がシビックプライドと重なり、プロモーションとして一元的に理念を掲げるだけではなく、図書館的な日常活動に落としながらそれぞれの市民の多様性を生かしたシビックブライドを掲げるのが良いと提言しました。
市民協働とシームレスに融合できているところがさらに良いですよね。
吉成:そうなんです。でも、メディアコスモスを一つにするのに5年かかりました。
イベントのやり方一つにしても、考え方が違いそこを”長期的で図書館的な考え方”に寄り添う形に変えていくことに苦労しました。
シビックプライドプレイスに置いている「岐阜な人カード」で、歴史上の偉人の隣に今岐阜市で活躍している人物を置きました。まだ名の知られていない美術家やアーティストを講師として招き、活躍する場を増やし、これから未来のある若者たちにスポットをあてていくのがメディアコスモスの役目だと思っています。
図書館長を引き受けたもう一つの理由は
吉成:知性・知恵を私たちが暮らす生活の事案にまでどこまで近づけられるのか。それぞれによそごとから自分ごとにするために図書館の中の”知”をむすびつけたいという意思がありました。図書館に来ない人たちにどう振り向いてもらえるものにするか、啓蒙的にならないもっと自由で楽しい方向へするのかということで読書推進教育自体のあり方をかなり変えました。
YA,児童に関する面積が多いのもそれがあってのことですか?
吉成:YAを少なくする図書館が多いですよね。児童館にいる頃からそう感じていました。
でも、ここは席数も多いしYAが勉強にも利用するための空間を作ったっていいじゃないか、”馴染むこと”が大切だと思い変えてきました。
こういった図書館があるとここに住んでみたいなという気持ちになります。
吉成:2‐3年目からメディコスがあるから引っ越してきたという方も多かったです。
他にもどうしても引っ越さないといけないという人が、ここと離れることが残念ですと言ってくださる人もいました。そう考えると、やはり図書館は身近な場所なんだなと実感させられます。
前例にとらわれず理念の元、新たな取り組みを率先して取り入れていく姿がお話を聞いていてよくわかりました。 今日はお忙しい中、色々とありがとうございました。