秋田県・東成瀬村教育委員会
学力トップクラスを支える東成瀬村の仕組み(1)
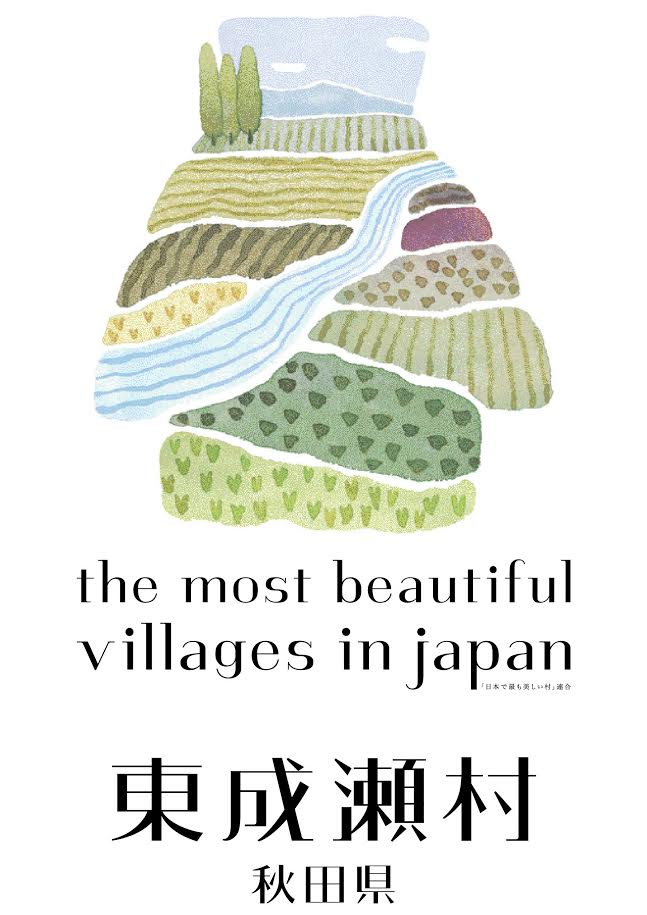
所在地:〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
電話:0182-47-3401
HP:http://www.higashinaruse.com/
東成瀬村
秋田県東南端に位置し、人口2600人余り、面積204平方キロメートルの村。「平成の市町村合併」には加わらず、「自主・自立」の道を選んだ。村営塾の開設や村単独で外国語教師を雇用するなど「学力日本一の村」「教育の村」として知られ、教育関係者や子どもたち、メディアなどの視察、取材が県内外や海外から多く訪れている。また、漫画家「高橋よしひろ」はこの村の出身で、国内外に多くのファンがいる。
教育委員会
教育委員会を訪問し、鶴飼教育長に教育への考え方、方針、取り組みを伺った。また、児童館では子どもたち(幼児~高校生)の読書教育について、実践的な活動の説明を頂いた。

鶴飼孝(つるかい・たかし)
1944年10月9日秋田県、生まれ。秋田大学教育学部英語科卒業後、東成瀬村立東成瀬中学校教諭、湯沢市立湯沢南中学校教諭、秋田県教育庁義務教育課課長などを経て、2006年から東成瀬村教育長。
(写真提供 東成瀬村)
参考
東成瀬村の「こども読書活動推進計画」は以下からご覧いただけます。
鶴飼教育長へのインタビュー
(敬称略)
鶴飼:これから必要な子供たちの力は、情報を構造化する力が必要だと思います。つまり、情報の量を増やすだけではダメで、それでは情報がどこに収まるかがわからない。私は英語の教師ですが、(動詞+ing)は、進行形、動名詞、形容詞も形は皆同じ。量が増えていくと子供たちは混乱する。機能をちゃんと教えないといけません。形は同じだけど、中身は違うということです。意味を教えて頭の中を整理し、膨大な知識をうまく納めてやらないと本当の力にならないと思っています。東成瀬村ではそういった授業を目指していますし、もちろんそのベースとなる知識やその裏付けも大切と考えています。具体的には東成瀬村では、子供たちが「さようなら」というとすぐに図書室に行く。さようならといった瞬間に本に触れられる、本を読む環境がそこにある。寝そべって本を読む子もいるし、宿題をやる子もいる。おしゃべりをしたりする子もいる。放課後になれば、児童館に寄って本を読むか、おしゃべりをするか、家庭学習を早くそこでやってしまうか(笑)そういう環境になっています。
いいですね。おしゃべりできるというのは大事ですね。
鶴飼:いいでしょう。(笑)文部科学省の方も、3年前に視察にこられたとき「面白い」と言っていた。一つの箱の中で、上は児童館、下は保育所。それを全部教育委員会が所管していますから。
厚生省とか文部科学省とかは直接関係ありません。管理も一元的にわたしたちがやれます。ここでの教育は、生まれてから中学三年生までは我々が統括できるからスムーズにやれます。いいアイデアを生むのが教育委員会の大事な仕事の一つだと思っています。
生まれてから中学三年生まで終始一貫した教育方針、教育制度の中で子供が育てられるという自治体って、あまり無いですね。
鶴飼:私たちの教育の柱は、小中連携教育です。小中連携はどこでもやっている。しかし、他が目指している「小中連携」とはちょっと違う。他は「不登校、いじめ」「学力低下」の解消といった目的。うちはそういうことはあまりなくても、小中連携をやっている。それはなぜかというと、人間が育つというのは、様々な異なる価値観に触れて、自分を分かって、見つめて、異なる者同士が議論をして、新しい価値に気づいていくという子供の生き方をさせた方がよい。ここでは生まれてから中三まで同じ顔触れだから、議論はそんなにしなくてもわかりますよ、暗黙のうちに。しかしそのまんまグローバル化と言われている社会に出ていっては太刀打ちできない。議論も情報入手もできないのでは困ります。ですから、小中の間に、とにかく異なる価値観に触れさせています。この観点から、「小一から中三まで、とにかく一つの学習母体にして様々触れさせて、考えさせる。」ということをやっています。キバナコスモス、徳育ってやったけど小一~中三までわざと混ぜてグルーピングしています。合わせて200人の子供しかいないが、パークゴルフやグランドゴルフに参加する地域の人、先生方を入れると300人くらいはすぐに揃う。そうなるとおのずと一緒に作業をしなくてはならない、黙っていても異質性に触れる授業であり教育活動になります。小学校で今年は一年生から六年生まで10グループ作り、清掃とか花植えなどをしています。日常的に異なるものに触れさせています。授業もそうで、課題をつかんでもらって一人一人に「僕はこう」という「僕」を持ってもらって、その次は発表させる。その後、議論をさせて、新たな価値に気付くという授業スタイルをとっています。これらの取り組みについて海外や全国から視察がきています。それと同じ観点でわたしたちは読書を位置付けている。読書から得られるもの、それは異質性です。今まで蓄えたものと違う世界と自分を向き合わせて一体どうなんだろうという力を身に付けることができます。
韓国、香港、モンゴル・・・そういった人たちに触れさせるのも、人は人のシャワーを浴びて人になると思っています。いろんな人がいるが、自分はそういった人と合わないからと遠ざかっていてはグローバル社会の中で生きていけない。
仮想化された実社会の逆の面がメリットになっているのですね。
鶴飼:現実はそうなんだから、それをどう活かしていくか?
小さい自治体というメリットがプラスになっているんですね。
鶴飼:私の考え方として、1+1は3でも5でもなるような希望をもって、やっていく必要があると思っています。
この児童館を建てられたのは、そういう思いがあったからでしょうか?
鶴飼:そうです。横とか縦の連携性というのが自然にできます。日常生活の中でそれが環境としてあるんだということ。例えば高校生がバスに乗るまでの時間があるので、しばらく児童館に居る。ここにいて時間を使い、本を読んだりおしゃべりをする。高校生がいるんだけれども未就学の子供もいます。自然にそういうエリアになっています。ここはそのようなエリアなのです。


